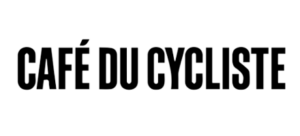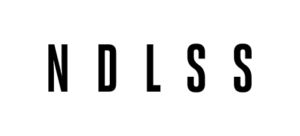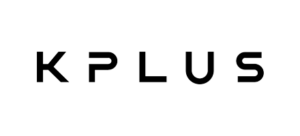S-Works Tarmac SL7は、発売から2年以上経過するにも関わらず、未だトップクラスのバイクとの呼び声高いモデルです。
既に多くのレビューコンテンツが存在しますが、本記事ではTarmacの歴史を紐解きながら、なぜSL7がこれほど乗り手を熱狂に巻き込むのか、その背景とTarmacの今後を含めて詳細に見ていきます。
レビュアー
 |
Ryuji(@ryuji_ride) |
text & photo/Ryuji(@ryuji_ride)
Contents
1. S-Works Tarmac SL7

Aero is Not Everything
スペシャライズドといえば、スポーツサイクルの世界では誰もが知るビッグブランド。
高いレベルのエンジニアリングに加えて、一流選手たちからのフィードバックと豊富な開発リソースの投資によって生み出される同社の製品は、常に時代をリードしています。
プロダクト開発だけに留まらず、マーケット分析に対しても熱心な同社は、新たなプロダクトをリリースするたびにユーザーの心を動かすコンセプトを打ち出してきました。
特に2018年、”Aero is Everything“と銘打って登場したS-Works Venge(第3世代)は、自社の風導実験施設Win Tunnelを活用して空力性能を向上させたモデルとして一躍脚光を浴びました。それに加えて、ディスク化で懸念された重量面や、前作Venge ViASで課題だった剛性感とコントロール性など、数々のマイナス要素を飛躍的に改善した結果、“名機”と呼ばれるほどのバイクとなったことは皆さんの記憶にも新しいかと思います。

ディスコンとなったVenge
しかし2020年、S-Works Tarmac SL7(以下: SL7)の発表と同時に、そんなVengeは潔くディスコン化されてしまいます。
代わりに登場したSL7は、究極のオールラウンダーという仕様。空力と重量というトレードオフの関係にある要素の両立を目指し、さらに高剛性なバイクという要素盛り盛りで、SL7があればVengeは不要とまでスペシャライズドは言い切りました。
空力・軽さ・剛性──いずれも速さという指標に繋がる要素なので、SL7の目指すコンセプトは真っ当なものと言えます。とはいえ、昨日まで「空力こそ全て」と言っておきながら「それはもう過去の話です」と言わんばかりの勢いで登場したSL7に対して、当初は懐疑的な意見もあったかと思います(とりあえずは、同社がそれだけSL7の性能に自信を持っているということなんだと受け止めました)。
ただ発売から2年以上経過した今、SL7はVengeを差し置いてトップクラスのバイクという評価を得ていることは疑いようもありません。
僕はこれまでS-WorksグレードのTarmacには、試乗も含めて初代から全モデル触れてきましたが、どの世代のTarmacも時代の最先端を行く魅力的なバイクだったと思います。かなり昔のモデルですが、SL2、SL3は愛車として所有したTarmacファンの1人です。
だから今回、三度心惹かれてSL7の購入に至りました。
S-Works Tarmac SL7スペック
| サイズ | 44/49/52/54/56 |
| コンポーネント | Shimano Dura-Ace R9270 Di2/SRAM Red eTAP AXS |
| ハンドル | Roval Rapide Handlebar, carbon |
| ステム | Tarmac integrated stem, 6-degree |
| サドル | S-Works Power |
| ホイール | Roval Rapide CLX |
| タイヤ | S-works Turbo Rapidair 2BR |
| 税抜価格 | ¥1,705,000〜 |
*記載価格は2023年3月時点のものです
ディテール

Roval Rapideハンドルバー。フラットポジションのバー表面にはテクスチャー加工がほどこされ、濡れても手が滑り難くなっている

フロントフォーク

ダウンチューブは極端な翼断面形状ではない

シートチューブはSL6と比べると扁平率が高く、エアロな形状に変化した

トレンドの小さいリア三角。シートチューブとの接合部は空力を意識した形状。ホイールは高速巡行を想定した高いリムハイト
S-WorksグレードのコンポーネントはSRAM Red、Shimano Dura-Aceの2択のみ。残るパーツのほとんどは、同社の最高グレードのオリジナルパーツで構成されていて、完成車の状態で6.8㎏に仕上がっています。
ディスクロードの重量感に慣れてしまった自分は、SL7を箱から出す瞬間、久しく味わっていなかった6.8㎏という軽さに心が躍りました。
純白のレーシングバイク

レース好きな方なら既知かと思いますが、上記の6.8㎏はUCIが規定で定めているレース用バイクの最低重量です。
リムブレーキが全盛の頃は、構造的にさまざまなパーツが軽く設計されていて、6.8㎏を容易に下回る事ができたので、鉛などで重量をかさ増しするケースも珍しくはありませんでした。
対して最近は、ディスク化によってバイク自体の重量が重くなる傾向にあるため、レースシーンでバイクに鉛を貼るような光景はほとんど見かけなくなり、むしろなんとかして軽量化しようという動きが強くなりました。
多くのメーカーが軽量化に苦戦する中で、SL7はフレーム以外も積極的に自社製のパーツで構成して6.8㎏を達成しています。これが示すのは、SL7とはUCIの定めるプロカテゴリーのレースでベストパフォーマンスを発揮するために設計されたレーシングバイクであるということ。
必ずしも僕たちアマチュアライダーの多様な用途に合わせて設計されているわけではないということは、最初に理解する必要があります。
2. Tarmacの歴史とコンセプトの変化

20年近い歴史を持つTarmac
初代Tarmacは2003年に登場しています。Tarmacの目指す方向性やコンセプトは世代によって少しずつ軌道修正されているため、その道のりを振り返り、今のSL7に与えられている役割を紐解いていきます。
Tarmacは、元々は「コンペティティブカテゴリー」というレーシングを広義的にカバーするモデルとしてカテゴライズされていました。
2004年には初代Roubaix、2011年には初代Vengeが登場します。コンフォートのRoubaix、エアロのVengeとそれぞれのモデルに明確な役割が与えられたことで、軽量高剛性化の方向に舵を切っていたTarmac。SL4までは「重量剛性比で、◯◯%向上」という軽くて硬いバイクを目指していました。
ここで注目すべきは、モデルごとの役割は違っても全てのモデルが「速さ」というベクトルに向かっていたという事です。
これはスペシャライズドが当時バイクを供給していた選手たち(トム・ボーネンやパオロ・ベッティーニら)からのフィードバックに従って、レースで勝つためのバイクを作ることが主な目的とされていたからだと考えられます。
一方、アマチュアライダーの中においては必ずしも全てのライダーがレースのリザルトを追い求めているわけではなく、むしろそういったライダーは限られた存在です。またサイクリングの楽しみ方の多様化に伴って、ただ軽くて硬いというバイクの需要は減少傾向になっていきます。
こうしたマーケットの動きを知ってか知らずか、SL5では“Rider-First Engineered(ライダーファースト・エンジニアード)”という設計思想を取り入れ、バイクのサイズ毎のライドフィールを調整します。レーシングバイクという位置付けを維持しつつ、アマチュアも含めた多くのユーザーが扱い易いフィーリングを副産物的に手に入れました。
そして2021年には新たに『Aethos』をラインナップに加え、レーシングから切り離したカテゴリーを確立。「速さ」ではなく「楽しさ」という価値をユーザーに提供します。
Vengeは第3世代で廃盤となりましたが、守備範囲の広いRoubaixは今後もマーケットの多様化に対応すると見込んで残留されたものと思われます。
そしてSL7は、再度レーシングカテゴリーを強く牽引する存在となったところが現時点だと考えられます。

“レーシング”の意味合いをより強く与えられた第7世代
3. インプレッション前段
昨今はバイクの性能を総合的に設計するために、ビッグメーカーを中心にオリジナルパーツで構成した、いわゆる“パッケージ売り”という形が増えてきました。
SL7も例外ではなく、こうしたバイクの性能評価の際にはパッケージ売り状態の評価を中心としつつも、純粋なフレーム性能についての評価を切り分けて行う必要があると思っています。
とはいえフレーム以外の全てのパーツを入れ替えてテストするほどのリソースはないので、今回はパッケージ売り状態のSL7に対して普段乗っているSuperSix EVO(以下:EVO)やここ2年間ほどで試乗してきたディスクロードとの相対的な比較をしていきます。

レビューはSuperSix EVOやほかのバイクとの相対評価となる
4. 全ての速度域で淀みなく速い

まずSL7の強みとして特徴的なのは、どの速度域でもしっかりと加速し、速さに淀みがないことです。低速域はもたついて高速域でよく伸びる、またはその逆、といった二者択一のバイクはよくありますが、SL7はそれらのバイクとは全く異なっていました。
トルクのかけ始めは、軽量高剛性なバイクのようにソリッドな加速をしつつ、スピードが乗ってくると今度はエアロロードのようにスピードが維持されて減速し難い感覚といえばイメージしやすいでしょうか。
実際のレース(特にクリテリウムやラインレース)では、チェーシング、ブリッジによる加減速や高速巡行など、様々なシチュエーションが想定されるので、SL7のように各速度域での弱点の少なさはライダーにとって大きな安心材料になります。
5. ペダリング許容角度が狭い

疲れてきてペダリングが雑になったりすることは誰にでもあることです。大抵そのような状況では脚部の筋力を使い果たし、身体全体でどうにかしてペダルに入力しようとするため、多くの人はケイデンスを低くして、重たいギアをごちゃついたフォームで踏み始めます。
極めて感覚的な話になってしまいますが、普段乗っているEVOや最近試乗したTREK Emondaなどは、バイクの振り易さやしなりなどによって、雑なペダリングを受け止める許容角度が広く、このような状況でもバイクを前に進めやすい感覚がありました。
対してSL7は、直進性の強さ故にそのような許容角度が狭く感じます。乗り始めた当初はその特性のせいで、非常に進めにくいバイクだと感じていましたが、何度も走るうちにSL7ならではの進め方を理解するようになります。
そのポイントを端的に言うなら、綺麗なペダリングの中で小刻みに入力することです。ダンシングも同様にダラダラと捻りこむような動きではなく、サクサクと小さめにバイクを振る方が進みやすいように感じています(もっと出力の高いライダーなら違う感覚が得られるかも知れません)。
6. コントロールには高いスキルを要する

ある程度は慣れの部分もありますが、ピーキーと紙一重な俊敏性をもつSL7のコントロール性は誰にでも扱いやすいものとは思えません。
極端な例ですが、車であらわすなら、僕たちのような一般のドライバーがいきなりオープンホイールのフォーミュラカーに乗って普通に乗りこなせるのか想像してみてください。
殆どの方は、足回りの硬さやパワーに慄き、ハンドルをどれくらい切ればいいのか、アクセルをどれくらい開けたらいいのか、恐る恐る運転することになると思います。
オールラウンドバイクと聞くと、誰にでも扱いやすいものと勘違いして捉えられることがありますが、SL7のオールラウンドはレース強度でのシチュエーションにおける万能性のことを指しています。つまり「その真価を発揮、体感するためにはそれなりに高いスキルを要する」ということです。
7. 乗り心地ははっきり言って良くない

ライダーとバイクとの主な接点は、ハンドル、サドル、ペダルの3点です。中でもハンドルとサドルからのインフォメーションは乗り心地に大きく影響を与えています。
まずハンドルから伝わる振動は、はっきり言っていい印象はありません。これは主にフォークやヘッド部の構造によるものだと思いますが、普段EVOで使用しているホイール「SL 45 KNOT」に付け替えると多少の改善は感じられたので、ホイールを変えたり、タイヤや空気圧を変えるなどして及第点に持っていくことは可能です。
サドルからの振動についてもEVOに比べれば突き上げ感は否めません。僕の場合はサドルをデフォルトのS-Works PowerからS-Works Power With Mirrorに変えることでかなり改善されました。
8. 狂気じみたスピード

路面状況によって性格が豹変するSL7。荒れた路面での扱い難さ、乗り心地の悪さはとてもストレスを感じますが、サーキットのように滑らかで平滑な路面での速さは、狂気じみたものを感じます。ペダルに力を込めて踏むというより、チョンっとわずかに入力していく感じでどんどん加速します。
またダウンヒルでも、全くペダルへ入力しなくても恐怖を感じるほどに加速していくので、ついブレーキをかけて減速したくなります。この下りの速さは、廃盤になったVengeのそれとほぼ同じものを持っていると思いました。
9. Rapide CLXの恩恵は大きい

RapideシリーズはRovalが長年煮詰めてきたモデルのひとつで、今作は前(リムハイト51mm、外リム幅35mm)後(リムハイト60mm、外リム幅30.7mm)という、リムハイトもリム幅も異なる今までにない組み合わせ。そしてこのリムハイトで前後セット1,400g(カタログ値)という軽さにも驚きます。
横風の影響やコントロール性を考慮しつつ総合的な速さを追求したこのスタイルは「空力、剛性、軽さ」というSL7が追い求めたコンセプトに沿うものだと思います。
そしてRapide CLXは実際このスペックが示す通りの働きをしてくれています。
軽さを生かした軽快な加速感やリムハイトによる横風の対応力と高速域での楽さは、どんな状況でも高いレベルで走ることができると感じます。
またDTスイス製36TスターラチェットのEXPフリーハブは、踏み込みから実際に加速するまでの感覚が速すぎずも遅すぎない、丁度いい塩梅に調整されていると感じました。
※ラチェットの歯数が多いほど踏み込みから実際の加速までのレスポンスが速くなります。
10. 最速を背負ったバイクのその先は

本レビューを書くまでにSL7には3,000kmほど乗ることができましたが、このバイクが手元に届いた時はたまたま新型コロナウイルスに罹患して間もない頃だったこともあり、脚力もかなり低下していました。
そのせいかSL7のファーストインプレッションは「乗りこなし難いバイクだな」とか「本質が全く見えない」という散々な状況でした。
徐々に体力が回復していくと少しずつSL7の良さを感じ取ることが出来るようになりましたが、最初から感じていた乗りこなし難さは今でも完全には消えてはいません。
いつまでも速すぎる下りは怖いし、疲弊した状態ではバイクの硬さに跳ね返される。
このバイクがどれほどに「生粋のレーシングバイク」であるかということを知らされたと同時に、自分はまだSL7を乗りこなすまでに至っていないのだと思っています。
繰り返しになりますがSL7のオールラウンダーの定義は、あくまでもレースという限定されたシーンにおける万能性を指していることは間違いなく、そこを目指さないユーザーからすればレース一辺倒のSL7は、かなり守備範囲の狭いバイクなのかも知れません。
しかしペダルを漕ぎ始めてからすぐに40㎞/h以上の巡行をしたり、チェーシングやブリッジ、コーナーの立ち上がりで加速する、さらにはヒルクライムもこなしていくようなシリアスな状況においては、SL7は絶対的なアドバンテージを持っています。

「速さ」という指標を純粋に追い求めたSL7。時代ごとに背負ってきた役割は様々でしたが、今スペシャライズドが考える最速という定義は何かと問うのであれば、それはSL7だと言えます。
そしてそんな最速バイクも未来に向かってまた変化していくことでしょう。そしてそのバイクを仮にSL8と呼ぶなら、僕はSL8にも引き続きこのスピード狂のような潔いコンセプトを継承して欲しいと思っています。
一台のバイクに”速さ”という一つだけの指標を追い求めることは、どんなメーカーでもできることではありません。Aethos、Roubaix、Crux、Divergeといったバイクを展開して、多様なジャンルを漏れなくリードできるビッグメーカーだからこそ、”速さ”だけに集中できていると感じます。
昨今のオールラウンダーと呼ばれるロードバイクは、乗り心地や扱いやすさと言った要素を取り入れて間口を広げているように感じますが、そんな時代だからこそ、これからのTarmacには完全に差別化された荒々しいほどの“ピュアレーシング”を僕は期待しています。
S-WORKS TARMAC SL7(スペシャライズド公式サイト)
text & photo/Ryuji(@ryuji_ride)