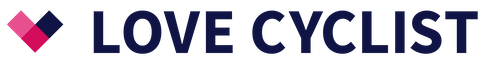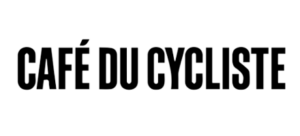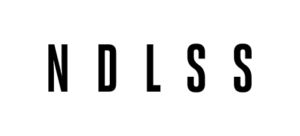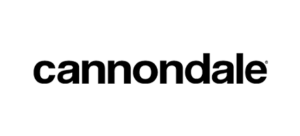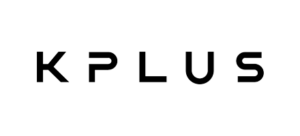お気に入りメーカーを見つけよう。
ロードバイクを選ぶときにまず悩むのが、どのメーカーにするかということ。
同じ価格帯で走行性能だけで見れば、エントリー〜ミドルグレードのモデルはメーカーによる差がそれほどありません。あったとしても、最初の頃は微妙な違いを感じにくいため、気にする必要はないレベルです。
そうなると、「自分の好きなデザインのバイク」という選択基準が最優先されます。
それは、ロゴデザイン・フレームの形状・カラーリングといったいくつかの要素から構成されるもの。
本記事では人気のロードバイクメーカーの特徴・ブランドイメージ・代表的なモデル画像を地域別にまとめているので、デザインの好みとあわせて、初めてのロードバイク選びの参考にしてください。
text/Tats(@tats_lovecyclist)
1. 北アメリカ
業界のトレンドをリードする北米ブランド。資本を活かしたデータドリブンな開発により走行性能は群を抜くため、特にシリアスレーサーが好んで選択している。
Specialized – スペシャライズド(USA)
業界にイノベーションを起こし続ける

S-Works Tarmac SL8
1974年に設立され、トレック、キャノンデールと並んでアメリカを代表するメーカー。ここ数年ツール・ド・フランスで最多勝利を挙げ続ける随一の技術力を誇る。
ストイックなまでに性能を突き詰めたハイエンドグレードS-WORKSにより、シリアスレーサーから熱狂的な信仰を集めているSpecialized。
高い完成度を誇ったエアロロード「Venge」をディスコンにしてレースバイクを「Tarmac」一本に絞ったり、UCIルールに囚われない斬新なバイク「Aethos」を開発するなど、常に業界にイノベーションを起こし続けている。
今後も業界のトレンドを知る上で、Specializedの動向は見逃せない。
TREK – トレック(USA)
実績も技術力も一流

Madone SLR
ツール・ド・フランスを7連覇したランス(ドーピング問題はあるものの)にバイクを提供していた実績や、最先端を行くカーボン成型技術で超軽量モデルを展開するなど、実績も技術も一流のメーカー。そしてSpecializedのライバル的ポジションにいる。
肉厚なフレームを持つエアロロード「Madone(マドン)」はTREKを代表するエアロロードであり、強いロゴの存在感もあって、ブランド全体としてとても男性的なイメージを与える。
トレック・セガフレードで活躍していた別府史之選手の影響もあり、根強いファンが多い。
Cannondale – キャノンデール(USA)
パフォーマンス×スタイルの先駆者

SuperSix EVO LAB71
Cannondaleは2020年頃からよりライフスタイルと親和性の高い自転車を展開するように方針を変更。Specializedがレースシーンの先駆者だとすれば、Cannondaleは自転車×ライフスタイルのシーンを率先して開拓している。ロゴをトップチューブに小さく配置したり、ライトとレーダーを標準装備する「SmartSense」を一部のバイクに搭載するなど、ユーザーライクなラインナップが豊富。
レースバイクにも注力しており、エアロモデルの「Systemsix」と軽量モデルの「Supersix」は新ロゴのスタイリッシュさを含めて業界の先端を走る高性能バイクとなっている。
またCannondaleは2021年にオランダのPon Holdings傘下に入り、本社もオランダに移転している。そのため「オランダのメーカー」と括るのが事実としては正しいが、マーケットの認識としては依然として「アメリカのブランド」となっている。
Cervélo – サーヴェロ(カナダ)
プロ向けの最速ラインナップ

Caledonia-5
フランス語の“cervello(頭脳)”と、イタリア語の“vélo(自転車)”を組み合わせたブランド名。
新開(兄)の影響で、このバイクに乗って相手を仕留めるバキュンポーズをすると必ず自分が敗けるというジンクスが巷に広まっている。しかし実際はTTバイク開発からはじまったブランドだけに、流体力学に基づいて設計されているカーボンフレームで多くの実績を残している。
頂点を極めるクライミングバイク「R5」や最速のパフォーマンスを発揮するエアロロード「S5」に加え、既成概念を超えたオールロード「Caledonia-5」も展開することで、新しい顧客層を開拓している。
Argon18 – アルゴンエイティーン(カナダ)
ロードレース界の新星

ロードレースのオリンピックカナダ代表として出場したジャーベス・リューが1989年に設立。
トライアスロンでの実績が多くサーヴェロと同様TTバイクのイメージが強いが、2015・2016年のツール・ド・フランスに出場したボーラ・アルゴン18が使用していたことでロードレース界でも注目を浴び始める。2017-2019年はアスタナが使用。
また2021年の東京五輪では、オーストラリアなどの強豪国がトラックバイクを使用していた。
現行モデルは、クライミングバイクの「GALLIUM」を進化させたオールラウンドバイク「SUM」を筆頭に、パフォーマンスを追求し続けている。
2. アジア・オセアニア
自転車生産大国として名を馳せている台湾が中心となるエリア。
台湾メーカーは横のつながりが強く、他ブランドの知見も工場に蓄積されているため、台湾ブランドのロードバイクは性能・コストパフォーマンスに優れているの特徴。
GIANT – ジャイアント(台湾)
間口の広い大手総合メーカー

TCR Advanded SL
1972年に創業した世界最大手の自転車メーカー。世界で初めてカーボンバイクを量産化したことで知られ、今では生産力とデータ力を活かしてコストパフォーマンスを最大化している。そのため他メーカーと比べて同価格帯でも品質は高い。
ライバルを凌ぐためのテクノロジーの錬成もトップクラスで、トータルレースバイクとして全方位型性能を持つ「TCR」や、世界最速の称号も手にしたエアロロード「PROPEL(プロペル)」が代表的なモデル。
また女性専用ブランド「Liv」も展開しており、150cm以下の女性も乗れるサイズがある。どんなサイクリストであれ、スタイルやニーズに合ったモデルが揃っている点は大手メーカーならでは。
MERIDA – メリダ(台湾)
ユキヤのブランド力を備えた総合力

Scultura 9000
Giantと同じ1972年創業の大手メーカー。工業デザインで世界をリードするドイツに研究開発の拠点を置き、レース現場の声をリアルタイムで製品開発に活かしている。設計から生産まで一貫して自社設備で行っており、そのため高品質のバイクを展開できる数少ないメーカーでもある。
また新城幸也選手が所属するUCIワールドチーム「バーレーン・ヴィクトリアス」や国内の「宇都宮ブリッツェン」に機材を供給していることでも人気。ユキヤのブランド力でロードバイク購入時にメリダが選択肢に入る方も多い。
空力性能と快適性を両立した超軽量オールラウンダー「SCULTURA(スクルトゥーラ)」やエアロダイナミクスと剛性を突き詰めたエアロロード「REACTO(リアクト)」などが代表的なモデル。
CHAPTER2 – チャプター2(ニュージーランド)
エスニックな雰囲気を持つ“第2”のスタイル

KOKO
ニールプライドのバイク部門を指揮していたマイク・プライド氏が、人生の“第2章”という意味を込めて2017年に創業したCHAPTER2。
勝つためのブランドを目指していたニールプライドとは異なり、CHAPTER2はスタイルも重視。通常カラーのフレームに加えてLimited Editionのカラーを展開することで希少性をコントロールしたり、あえてフレームセット販売のみとして、自分好みのバイクをディーラーと一緒に組み上げる楽しさをサイクリストに提供したりと、よりバイクを楽しむことに焦点が当てられている。
また創業者自身が163cmと小柄なため、女性やジュニアなどに向けた小さいサイズのバイクの展開も充実。
ネーミングやグラフィックデザインには先住民マオリ族の文化を反映。オールロード「TOA(“勝利する”の意)」やエアロロード「KOKO(“飛ぶ”の意)」などを筆頭に、エスニックな雰囲気のバイクが格好良い。
Anchor – アンカー(日本)
ジャパンブランドの堅実さ

RP9
ブリヂストンサイクルによるブランド。
日本人向けのフレーム設計やサイズ展開をしていたり、自分の体格に合わせて自由にパーツ交換できるシステムを提供していたりと、ミクロ視点の気遣いが日本企業らしい良いところ。
2022モデルの「RP9」は、“ポストヴェンジ”とも言われるほど欧米メーカーに並ぶパフォーマンスを持ち、国内ユーザーから高い人気を集めている。
3. ヨーロッパ(イタリア)
歴史のあるメーカーが多く、伝統を重視する傾向にあるイタリアンブランド。
わかりやすくブランド力のあるバイクが欲しいときは、イタリアンバイクはハズレがないし、レースにおけるトップクラスの実力も伴っている。
Bianchi – ビアンキ
確実な実力を備えるチェレステカラー

Oltre XR4
創業130年を迎える世界最古の自転車ブランドで、パンターニやジモンティなど伝説的なチャンピオンたちが、チェレステのバイクで多くの勝利を獲得してきた。近年も主要なレースで勝利を挙げ続け、勝負の世界における存在感は衰えることはない。
特に「Oltre XR4(オルトレ)」は、ログリッチやファンアールトなどユンボ・ヴィスマの選手の勝利によってそのパフォーマンスが実証されており、改めてビアンキの開発力の高さを伺うことができる。
一方日本国内ではエントリーユーザーを取り込むマーケティングにも注力しており、ユニクロとコラボしたり海の家を出したりと、ブランド認知の裾野を一般人まで広げている。クロスバイク〜エントリーロードのラインナップも豊富なので、街中でチェレステカラーのバイクに遭遇する確率が非常に高い。
PINARELLO – ピナレロ
高級ハイエンドバイクの代表格

Dogma F
多くのサイクリストが憧れるピナレロ。2016年にルイヴィトングループ傘下に入り、高級ブランドパワーに磨きがかかる。
近年のイネオス・グレナディアーズ(旧チームスカイ)の活躍から見られるように、ここ10年でツール・ド・フランスを7回制覇しており、実力もトップクラス。
フラッグシップモデルの「DOGMA」は、過去にロンドン・デザインアワードで金賞を受賞するなど、デザイン性の高さも一般層に認められている。アーティスティックな流線型のフォークも美しい。現行の「Dogma F」は、フレームセットだけで約100万円の価格設定であり、所有欲もパフォーマンスも同時に満たされる究極のバイク。
Wilier – ウィリエール
流麗な美しさを持つ伝統ブランド

Filante SLR
1945年に創業し、40年代後半にツールで数多くの勝利を挙げた歴史あるWilier。そのブランド名は、“Viva l’Italia Libera e redenta(=自由と繁栄のイタリア万歳)”というイタリア語の頭文字からとったもの。
オールラウンドモデル「Zero SLR」やエアロロード「Filante SLR」を筆頭に、流麗なロゴと綺麗なフレーム形状が特徴的。
2020年シーズンよりUCIワールドツアーチーム「アスタナ・カザフスタン」とパートナーシップを締結しており、今後もツールでの活躍が期待される。
COLNAGO – コルナゴ
ブランド価値の高い高級パフォーマンスバイク

V3-RS
かつて選手として活躍していたエルネスト・コルナゴが20歳のとき骨折により選手生命を断たれ、メカニックとして1954年に自分の店を持ったのがブランドのはじまり。
美しいフレームフォルムや手作業による芸術的な塗装などブランド所有の満足感は高い。「ただ速い」というよりは、堅実に力強く走り抜く芯のあるブランドイメージ。
ツール・ド・フランス2020と2021で連覇したポガチャルがオールラウンドレーサー「V3-RS」に乗っており、改めてその伝統と性能に注目が集まっている。
DE ROSA – デローザ
伝統を重視する世襲制ブランド

MERAK
伝統ある高級イタリアンバイクの一角を担い、ハートのロゴはステータスシンボル。
フレーム職人だったウーゴ・デローザが1953年に創業し、現在は息子であるクリスティアーノ・デローザが2代目としてCEOを務めている。バイクラインナップの中に孫のニコラスを名を冠したカーボンロード「ニック」を出すなど、世襲制が色濃いブランド。
2020年モデルからロゴを一新し、「レトロ・フューチャー」というコンセプトを掲げながら他ブランドとは違う世界観へと邁進。
Basso – バッソ
イタリアの匠がつくるハイセンスな重厚バイク

Diamante SV
イタリアメーカーの中では若い1979年創業。
プロチームへは機材供給しない方針のため派手な印象はないが、大々的な広告ではなくプロダクトの開発にリソースをあてることで、厳選したフレーム素材でクオリティの高いバイクをつくり上げるメーカー。その技術力は、最も見る目の厳しいドイツマーケットで受け入れられるレベル。
Bassoを代表するモデル「Diamante(ディアマンテ)」は、20年以上にわたりオールラウンドバイクとして進化を続けており、ディアマンテから派生したエアロロード「Diamante SV」とともにハイクオリティバイクとして名を馳せている。
重厚感のあるシルエットだけでなく、かつては人気アパレルブランド“MAAP”とコラボしたカラーを出すなど、グラフィックデザインのセンスの良さも光る。
CARRERA – カレラ
近未来的な独特の世界観

Phibra Disc
1960〜70年代に活躍した元プロレーサー、ダビデ・ボイファヴァとルチアーノ・バラキによって1989年に設立。
その代表モデルはなんといっても、離れた場所からも認識できるフォルムをした「PHIBRA(フィブラ)」。トップレーシングの世界からは離れており、限界性能を求めるようなブランドではないが、ロングライドもショートライドも楽しめる無二の存在として我々を今も魅了し続けている。
4. ヨーロッパ(ドイツ)
工業国ドイツのロードバイクイメージは何よりも”質実剛健”。イタリアンバイクと比較すると明確だが、デザインは色気よりも男性らしさが強いシックな印象。そして、モノづくり大国のプロダクトとして精度の高いラインナップが揃っている。
Focus – フォーカス
本格派モダンバイク

IZALCO MAX DISC 9
シクロクロスの世界チャンピオンであるマイク・クルーゲが1992年に創設した比較的新しいメーカーだが、近年のツールでもフランスのチームAG2R(アージェードゥゼール)に機材を提供し、多くの成績を残してきた本格派。
代表モデルはエアロロードの「IZALCO MAX(イザルコ・マックス)」。最新の技術を取り込んだフレームとモダンなロゴデザインからとても速そうに見える。
FELT – フェルト
飾り気のないブルー&ブラックフレーム

元モトクロスのメカニックでフレームの魔術師と呼ばれるジム・フェルトが1980年代に立ち上げた総合自転車メーカー(ジムは今も現役でセッティングを行っている)。ロゴデザインはブランドコンセプトである”FAST, LIGHT, SMOOTH – 速く、軽く、心地よく”にぴったりでよく目立つ。
ブルーやブラックが基調のフレームデザインが多い。ラインナップも幅広く、エントリーモデルは求めやすい価格なので若い男性がよく乗っている。
Corratec – コラテック
アルプスの麓で生まれる質実剛健バイク

CCT EVO
1990年に南アルプスで誕生したメーカー。アルプスの麓にある本社でバイクの研究・開発が行われており、かっちりとした硬派なデザインが特徴。
日本向けにはセミオーダーシステム「Japan Assembly」が導入されており、対象のフレームやコンポなどを選択し、国内で組み上げるという仕組み(ただし選べるモデルは限定されている)。
絶対流通数は少ないが、エントリーモデルは品質が良いので、稀に乗っている人を見かける。
Canyon – キャニオン
コスパ&実力備えた直販メーカー

Aeroad CFR
1996年創業と若いメーカーだが、完成車のオンライン直販というセールスモデルを定着させた先駆者。
購入やメンテナンスにある程度知識を必要とするが、他のメーカーの同一グレードと比べるとかなりリーズナブルに感じる価格設定。シンプルなデザインも素晴らしい。
ワールドツアー2チーム(アルペシン・フェニックス、モビスター)に機材供給し、マチューをはじめとしたスター選手で数々の勝利を挙げており、実力面でも申し分ない。
自分でメンテナンスしていける人であれば優良な選択肢になるし、Canyon持ち込みOKなショップもあるので、条件さえ揃えば有力な候補になる。
5. ヨーロッパ(フランス)
LOOK – ルック(フランス)
速さ×ステータスシンボル

795 Blade RS
1984年にロード用ビンディングペダルを世界で初めて開発し、1986年にはフルカーボンフレームをツール・ド・フランスで初導入して優勝を飾るなど、業界のスタンダードを積極的に開拓してきた由緒あるメーカー。そのモデルはナンバリングで区分けされており、エアロロードの「795」、軽量モデルの「785」、エンデュランスの「765」が揃う。
高いカーボン技術とプレミアムな価格帯から「一度は乗りたい憧れのバイク」というポジションにいるため、初心者よりもある程度乗り込んだサイクリストが選んでいる。
TIME – タイム(フランス)
最強のカーボンマシン

Alpe d’Huez 01
1986年にロードペダルメーカーとして設立。
大規模なマーケティングやレースへの機材供給を行わず、技術の精錬にリソースを割いてフレームの開発を行っている、100%Made in Franceのメーカー。
TIMEフレームだけが採用しているRTMというカーボン成形技術は軽量で強靭なバイクを生み、さらに宇宙服でも使用される柔軟で弾力性のあるベクトラン素材を含めることでしなやかな乗り心地を再現しているなど、至高のカーボンフレーム技術を持つ。大量生産には向かないため価格も高い。
フレームセットのみでの販売しかなく、LOOKと並んで高級バイクの両翼をなす。
Lapierre – ラピエール(フランス)
親しみやすいフランスの貴公子

Xelius SL 9.0
1946年に創設され、マウンテンバイクメーカーとして発展したのちにロードバイクを製造するようになった総合自転車メーカー。ラインナップはエントリークラスからハイエンドまで幅が広い。LOOKやTIMEがフランス貴族とすれば、ラピエールは庶民派のイケメン。もちろん上流階級と対等に渡り合えるセンスも備えている。
現在はフランスのプロチーム「グパルマ・FDJ」にも機材を提供し、グランツールやクラシックレースで数々の勝利を挙げている。
代表モデルは「Xelius SL(ゼリウスSL)」。シートチューブとシートステーが独立した美しいアーチ形状は、デザイン性だけでなく剛性や快適性を生み出す源となっている。
6. ヨーロッパ(その他)
イタリア・ドイツ・フランス以外のヨーロッパメーカーは、超高級フレームから実力派バイクまで国ごとの特徴が出ており、好みのロードバイクがあれば人と被りにくいので狙い目。
FACTOR – ファクター(UK)
洗練された新時代のハイエンドメーカー

Ostro V.A.M
2007年に創業にした英国のメーカーで、2017-2018年にフランスのチーム「AG2R」に供給され有名に。2020年以降は「イスラエル・プレミアテック」とパートナーシップを結んでいる。
航空宇宙産業から派生した工学技術を用いた最先端のカーボンファイバー製造プロセスを持ち、ロードバイクは軽量エアロモデル「Ostro V.A.M」や山岳モデル「O2 V.A.M」を筆頭に、レース用のハイエンド機種に絞って開発。
フレームのフラットデザイン、そして全メーカー中最も洗練されたFACTORロゴ含め、トラディショナルブランドにはない新時代らしさに溢れている。
SCOTT – スコット(スイス)
超軽量フレームで実力派向け

Addict RC Pro
もともとはスキーのストック製造から始まった会社だが、1980年代にMTBやロードバイクフレームの製造を始め、世界初のエアロハンドルバーを開発したり、超軽量のカーボンフレームをリリースし最高峰のレースで活躍するなど、その技術における評価は高い。2021シーズンからはワールドツアーチームDSMに供給しており、数々のレースで実績を挙げている。
軽快な上り性能とスプリンターのパワーに耐えうる高剛性も併せ持つ「Addict」、カムテール形状をいち早く取り入れた歴史的エアロロード「Foil」を筆頭に、ストイックに性能を追い求めるブランドというイメージが強い。
BMC(スイス)
華やかな実績を持つスイスならではの堅実バイク

Teammachine SLR01
1986年に設立されたBMC(Bigelow Mounting Company)。当初は英国のブランド「ラレー」の販売代理店だったが、1994年から自社ブランドの製造を始める。
「iSC」と呼ばれるコンパクトなリア三角はBMCフレームの代名詞だったが、現在はその形状が快適性や反応性の面から最適解とされ、多くのメーカーが取り入れるように。
代表モデルは初代発表から10年が経つ「Teammachine SLR01」。ツール・ド・フランス総合優勝や世界選手権制覇、オリンピック金メダル獲得など華やかな実績を抱え、2021年からはフランスのワールドチーム「AG2R CITROEN」とともに活躍が期待される。
RIDLEY – リドレー(ベルギー)
クラシックレースに強いブランド

Noah Fast
自転車が国技のベルギーで1990年に生まれたメーカー。ベルギー籍のチーム「ロット・スーダル」との長年の協力関係を通して、プロツアーでの存在感も大きい。
国内では東堂の影響で一躍有名になり、女性人気も集める。
クラシックレースやシクロクロスレースを開催するベルギーを拠点にするため、荒れた路面に対応するバイクの開発に定評がある。それを代表するモデルが石畳での走行実験を通して生み出されたエンデュランス系の「Fenix」。加えてエアロロード「Noah」、軽量オールラウンド「Helium」を揃え、欧州トップブランドの一角を担う。
BH(スペイン)
玄人好みの本格派

G8 Pro
BHは“Beistegui Hermanos(ベイステギ兄弟)”の略で、第一次大戦中にベイステギ3兄弟が設立した銃器の製造会社が、戦後に自転車を製造することになったことが始まりとなる歴史的なメーカー。現在BHグループは自転車以外にも、銀行・切削機械製造・家電製造などさまざまな事業を抱える巨大企業となっている。
その代表モデルはエアロオールラウンドの「G8」。グローバルコンセプトモデルである「G」シリーズは、これまでインテグレーテッドシートポストなどの先進的テクノロジーを採用しており、G8はその系譜を受け継ぎ、エアロダイナミクスや剛性をブラッシュアップしている。
ORBEA – オルベア(スペイン)
山岳ステージに強い総合メーカー

Orca
1840年に創業し、BH同様元々は銃器製造メーカーだったものが、1920年から自転車の製造を開始。現在ではスペイン最大級の総合自転車メーカーになっている。
本社のあるバスク地方はピレネー山脈の麓にあるため、山岳でその性能を大いに発揮すると言われている。その代表モデルはオールラウンドバイク「ORCA」。山岳では軽さだけではなく、登りでの高いトルクを推進力に変える剛性と、下りのスピードを伸ばす空力性能が重要であるという設計思想が特徴。
ロードバイクが初めての方はこちら
※買う前に必要な情報から、買ってからロードバイクを楽しむための基礎知識を体系的に知ることができます。
著者情報
 |
Tats Shimizu(@tats_lovecyclist) 編集長&フォトグラファー。スポーツバイク歴12年。海外ブランドと幅広い交友関係を持ち、メディアを通じてさまざまなスタイルの提案を行っている。同時にフォトグラファーとして国内外の自転車ブランドの撮影を多数手掛ける。メインバイクはStandert(ロード)とFactor(グラベル)。 |