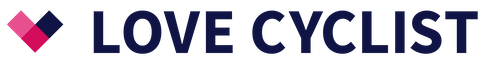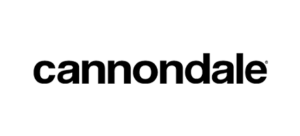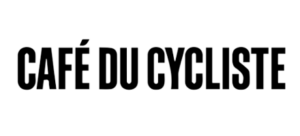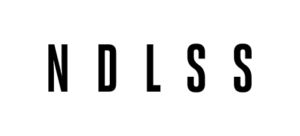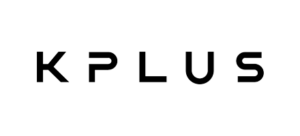コックピット周りはポジション、コントロール、空力といったライド体験全体の性能を大きく変える。そしてライド中常に目に入るので気分にも影響する。
それらすべての要素を最大レベルに引き上げるために、デンマークの『Polymer』による一体型ハンドルバーを選んだので詳細をレビューする。
text & photo / Tats(@tats_lovecyclist)
Contents
スペック

Sculpture Handlebar(税込¥135,300)©Polymer Workshop
「Polymer Workshop®︎(ポリマーワークショップ)」はデンマークのコンポーネントブランド。レーシングバイクの性能を引き出す最先端のコンポーネントを開発・製造し、ホイール、ハンドルバー、シートポストなどを取り揃える。
『スカルプチャーハンドルバー』の特徴は、エアロポジションに最適化されていること。ハンドル幅は360/380mmの2種のみで、リーチが一般的なハンドルよりも10mmほど長い。ステム角が一般的なものよりも低めの-10°設定。見た目が水平に近づき、より前傾を取りやすい攻撃的なポジションになる。バイクをよりレーシーな味付けにするプロダクトだ。
もちろんケーブルはフル内装で、すべてのヘッドセットカバーは3Dプリントで成形され、各フレームに最適にフィットするよう様々なサイズのスペーサーが付属している。
| ハンドル幅(ブラケット) | 360mm / 380mm |
| ハンドル幅(ドロップ) | 400mm / 420mm |
| フレア角度 | 9° |
| リーチ | 90mm |
| ドロップ | 130mm |
| ステム長 | 100mm / 110mm / 120mm / 130mm |
| ステム角度 | -10° |
| ステア径 | 1 1/8″ |
| 重量 | 320-340g |
| 価格 | ¥135,300(税込) |
導入の目的

一般的にサイクリストが一体型ハンドルにするのは、格好良さ以外に理由はない(あと空力と重量の要素もちょっとだけある)。
以前のロードではハンドル幅400mmを使っており、昨年Standert Kreissäge RSに乗り換えるタイミングでハンドル幅を狭くしたかったが、いきなり一体型ハンドルでポジションを変えるのは抵抗があった。そのためDedaのアルミハンドル(芯-芯で380mm)で暫定的に組んでもらい、狭いハンドル幅の感覚を覚えた(最初だけ違和感があったがすぐに馴染んだ)。

最初はDedaのアルミハンドルで狭いポジションに慣れる
ただDedaのハンドルはドロップ部分がフレアになっておらず、ドロップポジションのときに力をかけづらい。
380mm以下を取り揃え、ドロップ部分のフレアが大きい一体型ハンドルバーで候補に残ったのは、ENVEとPolymerの2つだけだった。
その中で、ちょうど2025年に発売されたStandertの新モデル完成車が、Polymerハンドルバーのオプションを用意していたため、ブランドの相性を考えてPolymerが残った。

ハンドル幅は360mm。Polymerを取り扱うショップMAGNETに相談したところ、以前取り付けていたDedaのステムのスタックハイトが低く、それに合わせてコラムカットしていた影響で380mmは取り付けできなかった。より狭くなることに不安はあったが、360mmはPolymerの思想を最大限に体験できることから換装を決めた。
ちなみに360mmでもUCIの新ルール(ブラケット内側280mm以上、ハンドルバーの全幅400mm以下)には適合するので、UCIレースに出る場合も問題ない。
Pros & Cons
Pros
バイクとの一体感:400mm→380mmにしたときにまず感じたが、狭くなったことでステア入力がよりダイレクトに伝わるようになった。360mmでさらにそれを感じており、より自分のバイクを思い通りに操作できている感覚がある。カメラを構えるときの安定性が不安だったが、実際に走らせてみると全然問題なかったのはよかった。逆に400mmハンドルのグラベルバイクに乗ると広すぎて違和感しかない。

バイクを意のままに扱える一体感
エアロポジションの最適化:Polymerは一般的なハンドルよりも10mmほどリーチが長く設定されている。これはエアロポジションを最適化するための設計だが、リーチが長いことで肘を曲げたエアロポジションがサポートされて楽になる。長時間先頭を引くときのメリットになる。ちなみにリーチが長いとステム長を稼げないから見た目が良くないという意見もあるが、これは好みの問題だ。

リーチが長いことで前傾維持が少し楽になる
アグレッシブな握り:ステム角が-10°なので、よりアグレッシブなポジションになる。ブラケット部を握ると未だに前傾が深いなと感じるが、このステム角のおかげでドロップ部を握ったときに力が入りやすい。ドロップは130mmと浅めで、ドロップ部分への移行がしやすい。これら総じて、アグレッシブな前傾ポジションを維持し続けるために設計されたことがわかる。

相当攻めたポジションになる
高い剛性感:特にスプリントやダンシング時に力を逃さず前に進ませる感覚がある。縦方向のしなりも少なく、荒れた路面ではやや手にくる場面もあるが、高速巡航ではこの硬さが安定感につながる。

レーシング性能を突き詰めている
空力の改善:定量的な効果は測れないが、ハンドルの後方に手のひらをかざすと、丸ハンドルよりも一体型ハンドルの方が空気がスムーズに流れているのが感じられる。丸ハンドルは空気が暴れている(2つ持っている方はやってみてほしい)。体感的に40km/hを超えたときの高速域が伸びやすくなり、平坦が楽になった。バイクの空力を改善するには、コックピットの最適化が一番コスパ良いと言われているが、それを実感している。

前方投影面積が少なく空気が流れる造形
軽量化:Dedaのステムとハンドルを使っていたときよりも155g軽量化し、コックピットが軽くなっている。

一体型ハンドルは軽くなる
格好良い:格好良ければすべてが解決する。これがすべてだ。“Sculpture=彫刻”というモデル名からも感じられるが、曲線で構成された造形が非常に美しい。これはPolymerのプロダクトでしか味わえない。

ステムまわりの艶かしさ
Cons
バーバッグが使えない:サイコンマウント形状の影響で使えない。空力空力と言っておいてバーバッグを使おうとするなという話だが、撮影するときには替えのレンズを入れるためのバッグが必要になる。そのため撮影時は、フレームバッグを取り付けるか、丸ハンドルのグラベルバイクを使うようにしている。

専用マウントはFramesandGear®製(別売)。GoPro/ライトマウントの接合部が根本にあるため、重いものを取り付けたときに折れにくい構造になっている
結論

速くて格好良い。ロードバイクの根源的な価値を最大限に高める選択となった。
昨年Standertに乗り換えたことで、しばらく落ち着いていたロードバイク熱が再燃したが、Polymerがその喜びをさらに一段階上へと連れて行ってくれた。
今もドロップバーを握るたび、走りながらコックピットに視線を落とすたびに心躍る。
Polymer Sculptureハンドルバーを購入する(MAGNET)
著者情報
 |
Tats Shimizu(@tats_lovecyclist) 編集長&フォトグラファー。スポーツバイク歴12年。海外ブランドと幅広い交友関係を持ち、メディアを通じてさまざまなスタイルの提案を行っている。同時にフォトグラファーとして国内外の自転車ブランドの撮影を多数手掛ける。メインバイクはStandert(ロード)とFactor(グラベル)。 |