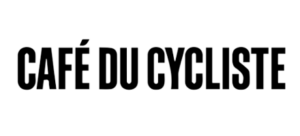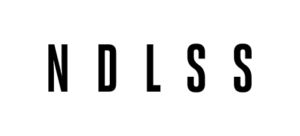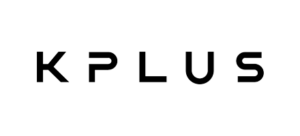サイクリングの途中で一緒に走っていた仲間が「あ、弱ペダ女子」とつぶやいた。
前方にはRidley、Bianchi、Giantに乗った少し垢抜けない感じの女性3人組が信号待ちをしていた。頭の中で『東堂』『荒北』『ゴッドハンド』というキーワードが駆け巡る。サドルの下でキーホルダーが揺れ動いているのが見える。みんなそれぞれ好きなキャラのバイクに乗って原作と同じシチュエーションを楽しんでいるのだろう。微笑ましいな。
しかしすぐそのあとに、こういう捉え方は彼女たちに対して少し敬意を欠くことなのかもしれないと思った。
信号が変わり、彼女たちは僕らとは違う方向に進んでいったけれど、慣れた足つきでビンディングペダルをパチッと順番にはめ、綺麗にトレインを組んでゆるい坂をスムーズに加速していくのが見えたのだ。それは昔みかけた弱ペダ女子の姿とは全くの別モノだった。
アニメ1期が放映していたころにたくさんいた弱ペダ女子。今でも彼女たちを見かけることが稀にあるけれど、そんなときどうしても最初に腐の感情で見てしまう。
「あ、弱ペダ女子」と仲間は言った。
そこには小馬鹿にするニュアンスが含まれていた。僕も少なからずそのニュアンスに同調していた。
2〜3年前にロードバイクを始めた身近な女子の中には、部屋の中でロードバイクがインテリアになっているケースがいくつもある。そんな状況を知っていたから「どうせ」という感情が先回りしてしまった。
しかしあそこにいたのは弱ペダ女子の数少ない生き残りだった。
ここ数年の弱ペダ女子ロワイヤルを生き抜いて、いちサイクリストとして自立した存在となっていたのだ。
弱ペダきっかけでロードバイクに乗り始めて今まで続けているということは、積算走行距離が1万kmを超えている可能性もあり、それはすでに初心者の域にはいないレベルだ。そんな彼女たちを人を食ったように見ていたということ。
僕たちは自分の思い込みに赤面した。
彼女たちはもう「弱ペダ女子」を越えた存在なのだ。
弱虫ペダルが好きで始めた彼女たちは、弱ペダのキャラと同化することだけでなく、ロードサイクリングそのものを本気で楽しむことを両立していた。それを「弱ペダ女子」という枠組みに抑え込むことなんてできるはずがない。
僕たちは最初彼女たちを見かけたときに自分の中で浮かんだイメージを悔やみ、彼女たちの前で許しを請いたいと思った。でももう彼女たちに会うチャンスはほとんどないであろうことを考え、胸が張り裂けそうだった。
僕たちは混乱していた。
『でももし今度彼女たちに再び出会えたとして、そのときどう呼べばいいのだろう?』
弱ペダ好きで、かつ本気の彼女たちに「弱ペダ女子」という否定的なニュアンスがこもったワードを当てはめるのは失礼にあたるのだ。敬意を込めて彼女たちを表現できる呼称はないだろうか。
しばらく考えても彼女たちを呼ぶ最適な言葉が見つからなかったけれど、いつかまた彼女たちに会うことができたら、せめてもの敬意を表して「弱ペダ女子さん」と呼ぼうと僕たちは誓った。
そしてゴッドハンドを繰り出したあとの福富と同じような態度で、うやうやしく謝罪の言葉を伝えるのだ。
*
「弱ペダ女子さん、あなたのことをただの腐女子だと思っていた。本当に…ごめんなさい」
彼女は東堂を目の前にしているかのようににっこりと微笑みながら答える。
「あなたが弱ペダ女子と呼んだ事実に対して、私は何も興味を持っていないし、何かを言う権利もないわ。ひどく限定的な世界の中で考えるのなら私はあなたを軽蔑するのかもしれないけれど、みな等しく自らのレゾンデートル(存在意義)を見つけるために愛憎の対象を求めているの。そこでは弱ペダ女子はただの弱ペダ女子として存在している。」
「メタファー」と僕は言った。
「これまでもあなたのように私たちをひとつの事象として括り付けようとしてきた男は何人もいたわ。優しく語る人もいたけれど、多くは暴力的な決めつけ。謝罪から始まったあなたにはまだ許される猶予が残されている」
僕は次の言葉を探す。
「これから僕たちはうまくやっていけるのだろうか?」
「そうね。ただひとつだけ言いたいことがある。それはあなただけじゃなく、私を見る全ての男に伝えたいことだけれど」
「何?」
電波の途切れたような沈黙の間を少し置いて彼女が答えた。
「完璧な腐女子などといったものは存在しないの。完璧な絶望が存在しないように」
*
そうして僕らは、すでに弱ペダ女子ではなくなった弱ペダ女子のことを考えながら、その日のサイクリングのくたびれた帰り道のペダルを所在なげに回し続けた。まるで彼女たちへの懺悔が、重くホイールのリムにひきずられているかのように。
(完)
弱虫ペダル(49): 少年チャンピオン・コミックス (2017/2/8発売)